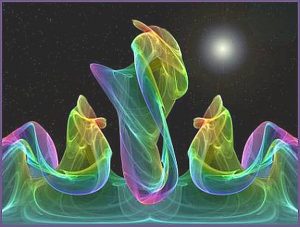サハラ砂漠紀行
志村 ふくみ 様 先だっては、世にも美しいお手紙を頂戴し、本当に嬉しく存じました。
また、音楽会にもわざわざお越しくださいまして、誠にありがとうございました。
こちらこそ、とても心に残る時を過ごさせていただきました。
志 村 様とお話しさせて頂いてます折に、ふっと遥かむかしに体験した忘れ去ることのできない大切な思い出がよみがえってきました。
この場で、二十数年たくさんの方にお目にかかりましたが、お話ししている最中、お相手の方の瞳の奥を覗き込んでいるうちに、時おり同じことがフッと甦ってきます。
それは若い頃、やむにやまれぬ思いにかられて訪れたサハラ砂漠で体験したことでした。
当時は、全国で大学紛争が吹き荒れ、新宿駅や東大の安田講堂が燃えたり、実存主義のサルトルの来日が新聞のトップ記事になるような熱を孕んだ時代でした。
世の中は、コップの中の嵐のように様々な主義主張が錯綜し、その乱れた渦の中で、私は悩みを深め、まるで磁気嵐に襲われ極北を見失った哀れな羅針盤のように、ただただ震えていたのを今でも覚えています。
ただそんな中でも、日本に初めて紹介されたアルベルト・ジャコメッティの作品「Isaku・Yanaihara」像から受けた衝撃に導かれるまま、私の終生にわたる恩師、哲学者・故矢内原伊作と出会えたこと、
また学生時代4年間読み続け、今も目の前に開かれる世界の中にその美しい1冊の本を読み解いているような、メルロー・ポンティのたった48ページの『眼と精神』、
その中で若き未熟な心には、まるで神託のごとく思われた“世界内存在”という一つの言葉に出会えたことは、私の生涯の天空を決めることになりました。
また、バリケードの中の不毛な嵐に心を寒くしていた折りに触れた、チュニジアの砂漠で色彩の神秘を体験した画家パウル・クレーや「知恵の七柱」を書いたアラビアのロレンス、
「僕は二十歳、この季節を人生の一番幸せなときだなどとは、誰にも云わせない」という美しい冒頭句で始まる「アデン・アラビア」を書いたポール・ニザン、
そして人類が初めて書きえたような言葉の星座を煌めかせる「地獄の季節」 「イリュミナシォン」を「それらは糞だ」と自らの若きヴィジョンをののしりながらも、その予言をそのままにアラブの地を生きたランボー!
彼等がその生を輝かしめるヴィジョンを生み出す契機となった砂漠への憧れは、生涯忘れえぬほど強烈な刻印を私の心に残しました。
教育された感情の方向から未開の感情の深みへ、その未踏の星座の煌めく宇宙へ行ってみなければ、人間はなにも解ったことにはならない。
この辻まことの言葉ほど、当時の私の心をその血の一滴に至るまで震撼させたものはありませんでした。
これはまさに『無知の知』、哲学の永遠のテーゼであり、社会性というお仕着せの服の中に押し込められた、自らの脈動する野生の生命を解き放つ唯一の武器であり、彼等を砂漠へ出立させた動機だと思いました。
生命の存在を許さぬ灼熱の地獄で、彼等はいったいなにを見たのか、なにが彼等を導き、彼等の命を見事に開花させたのか!その砂漠の大地の上に輝く豊饒なるものの、その聖なる正体に触れてみたい、それはきっと私の命をも開くものになるだろう。
この切なる願いを胸に、魂の本能の命ずる憧れに導かれるまま、私はチュニジアからアルジェリアを経てマリまで、地の果てにあると云われる大断崖バンディアガラに住む、神秘的な星の神話を今も生きるドゴン族を訪ねて、
『 心の対者 』となるであろう太陽と砂の大海・サハラを、キャラバンと共に縦断する、自らが心の中に作った聖地,『 未踏の星座の煌めく宇宙 』に向けて巡礼するような旅に出かけたのです。
しかし、人が出会う自然の場と時の中には、人が決してその足を踏み入れてはならないと思える場合があります。果たして砂漠に足を踏み入れていいものだろうか、この私が…?。未だ見ぬ世界へのとまどいを感じていました。
手元の古びた一枚の写真は、R・シュタイナーの人智学の権威として著名な高橋 巌 先生が「西岡さん、この写真には妖精が写っていますね!」と、おしゃったものです。
ある冬の満月の淨夜、いまだ私も3度しか見たことがないのですが、大きな窓の外に蛍の火のような薄緑の揺らめく炎に包まれた神秘的な“ 緑の富士”がありました。
目前の林の雪原に写る木々の繊細なレース模様のシルエットが、まるで目に見えぬ時の姿そのままに生き物のように微妙に移りゆくのを見て、思わず撮ってしまった写真です。
ところが、シャッターを押した瞬間、私の中に思いもかけない感情が起こりました。
それは取り返しようのないことをしてしまった!という胸をえぐるような後悔の念です。
たった窓ガラス一枚を境に外は、こちらの世界とは在りようが全く違う、時の流れさえ外れた異界と化していました。
青白い月光は外の世界を、賢治が「全く私の手のひらは水の中で青白く燐光を出していました。」と歌った“氷相当官の過冷却の水”、この溶けたプリズムのような不思議な水を満々とたたえたマルサロワール湖の青一色の水中風景のごときものに変えていたのです。
林はまるで水草のように月光の湖水の中を揺れていました。
チベット高原最深部に在る、インドラ神(帝釈天)の住まう世界の中心・須彌山(しゅみせん)に例えられ、世界の四大宗教の聖地であるカイラス山。
そのカイラスの母乳を湛えたアジアの4大河ガンジス、インダス、プラマプトラ、黄河の偉大な源、深海から世界最高位とされたチチカカ湖を遥か下界に標高4590mに浮上し、零下十度にも凍らぬ“マルサロワール”。
『ここではあらゆる望みがみんな浄められている。願いの数はみな寂(しず)められている。重力はお互いに打ち消され冷たいまるめろの匂いが浮動するばかりだ。』賢治がこう歌った天上の瞳、眼前の世界は今まさにそれの降臨でした。
月の光りの妖精が魔法の粉をふり、落ち葉一つに至るまでそこに在ることを誇るかのようにほのかな燐光に包まれているようでした。
この神々しい光景を目にしてはいけない。私の意識がその場にあることを気取られれば、この秘めやかな営みは即座に止み、その聖なる生き物はたちま ちその命を失うであろう。人の息ひとつ、小指一本さえその場に触れれば、それらは“青白く燐光を出して”共に燃え尽きてしまうに違いない。
私は盲しいた後にしか、この光景を見てはいけなかったんだ!と、切なる祈りのような思いがわきおこり、私はその珠を胸に納めました。
しかし、後日その写真を見たとき、この心を哀れに思ったのか、小さな形見がそこに残されていたのです。

私が心に誓った砂漠の旅は、このような人が触れてはならぬ自然の厳粛な神殿に、この小さき魂と肉体を捧げても悔いはなし!という、私にとって’清水の舞台’でもなお足りないほどの一世一代の覚悟を強いるものでした。
背中にしょった荷物の中身は、隠しもできないたった一つ、小さき命一つのみ、身を守る術も手だてもなく、想像を絶する50℃をこす灼熱の救いのない不毛の大地を歩む旅となります。
この触れてはならぬものに触れ、生死に関わる危険を冒す旅に、ハッと我にかえると身がすくみ、為さない自由もあるのだと何度も引き返す誘惑にから れましたが、そんな私を励まし夢を果たす勇気を与えたのは、他ならぬキャラバンを率いる’砂漠の民’ベドウィンたちの覇気に満ちた黒い瞳と、まさに’砂漠 の船’ 駱駝の決死の旅を前にしてナンの恐れもなくのうのうと横たわる姿でした。
私を見る彼らの瞳は微笑むように落ち着いていました。それは砂漠こそが彼らが何千年にわたり生き抜いてきた王国、故郷であることを教えていたのです。その微笑みを見たとき、私は彼等に守られている限り、旅を全うできると確信しました。
ベドウィンは、人間の生存には過酷な砂漠をあえて選び、そのバドウ(地獄)を住み処に彼等の家系図ではアダムにつながる太古より、歴史を生き抜い てきた勇者です。彼等が胸にかざしたジャンビア(三日月刀)は、偉大なる砂漠と、その聖なる地に生きる民である民族の誇りを証するものです。
彼等は、砂漠という大自然の不可侵の国境によって守られた、アフリカ大陸北部からユーラシア大陸深部に至る広大な王国を自由に遊牧、往来し、自ら の王国の不毛により、民族の伝統と血の純潔を守り、一切の余分なものをそぎ落とした骨と神経と筋の固まりである見事な肉体と’ハーマーサ'(剛勇と熱情) と云われる彼等の高貴な精神を作り上げたのです。
彼等は厳しいものに打ち勝ち生き抜いてきた民族としての誇りから、彼等の庇護無くしては生きられない砂漠の客を ‘ディヤーファ(客人好遇)’の美徳をもって迎えます。
彼等に迎えられることは、まさに砂漠自らにその偉大なる門をくぐることを許されることであり、私のサハラの旅はここに始まりました。
赤や黄や黒の原色、金やスズや銀、太陽やカルタゴの海、永遠なるものへの憧れを秘めたチュニジニアンブルー、そして黄土色や赤茶けた大地…。
異国を訪れ、一番始めにその異文化の鮮烈な洗礼を受けるのは、その風土に特有の色彩です。
初めて訪れたアラブは、まずは大地と空の色からして、私の常識を壊しました(笑)。そして、ここが大砂漠の重力に支配される地であることをあらためて私に教えたのです。
この信号機の赤と青がひっくり返るぐらい色の文法が異なるアラブの街で、不用意に目を開くことは、壊れた万華鏡を無理に覗かせられたような支離滅裂な印象にめまいをおぼえるほどでした。
しかし、この私達の許容の域をはるかに超え、熱を帯びてあふれかえるアラブの色彩の魔力に幻惑され、いつしかそれを愛するようになるのに、そう時はかからなかったのです。
“旧 約”の悠久の時代から漏れてくる、時にあせた没薬や乳香の香り、人を蠱惑するブロンズ色のなめらかな肌から薫る香油、アラブの男どもの太鼓 腹をつくる秘薬めいた食物のスパイスや炒られた油の匂い、ラクダの獣臭や羊肉臭、ひからびた大地にしみこんだ計り知れない量の血と汗の匂い、甘く爛熟した 熱帯の夜にむせかえる花の香り、そしてそれら全ての上を超越し、吹き抜ける大砂漠サハラの存在を教える風…。
私は、この偉大なる香りにあらがう術もなく引きつけられ、おののきながらも至高の地サハラを目指して、魂の本能の命ずるまま一歩一歩、心の中の階段を登っていきました。
大サハラの頭部を飾る花飾りのように点在するこれらアラブの世界は、五感を刺激する全てのものが大気の熱にあぶられ、エロスとタナトスが織りなす 七つのベールを舞うサロメのあらわな美しい臍が、喧噪と混沌の渦の中を、すべての耳目を引きつけながら奈落の底に落ちていくように“タブラ”( 魂の恍惚 )の大鍋に落っこちて、ごった煮されているようなものでした。
しかし、時まさしくモスクの天を指さす美しいミナレット(尖塔)から、祈りを呼びかける“アザーン”の声が響きわたり、クルアーン(コーラン)の 祈りの読唱が永遠に続くかのようなアラベスクの尾を引きながら大気に溶けて町を覆うと、それまで四方八方ハチの巣を突いたような喧噪で、町全体がうるさい 大いびきをかいてるような騒ぎは、巨大なアラブのランプに吸い取られ、万の群衆がうごめき、ざわめくスーク(バザール)もなにも辺り一面を深い聖なる静寂 が包みます。目の前の同じ町が、瞬時のうちに魔法のようにこの世のものとは思えぬものに変わりました。
曙の礼拝(ナンと、丑三つ時を少し過ぎた3時から4時過ぎ!アラブを旅する人の悩みの種です、笑)から夜の礼拝へ、一日5回の「アッラーヘアクベ ル」神は偉大なり)の言葉と共に、立ち、ひざまづき、両手を前に頭を深く拝する祈りの姿は、目に見えぬ彼等の魂の中の美しい出来事を私に見せました。
彼等の頭蓋の中の宇宙を、いま思いを託された白鳩が天に向けて登り続け、光りの中に溶けていきます。やがてそれは天の慈雨と化し、彼等の胸の中の母なる大地に降り注ぎ豊かに耕す、このメビウスの輪のような魂の営みを感じさせました。
この人々の祈りの思いが異邦人の私の肌を包み、つい先程までのむせかえるような熱気さえ、モスクのファサードを飾る神秘的なアイスブルーのタイルのような涼やかな冷気に変わり、共にこの身を包むのでした。
この聖と俗の融通無碍こそがアラブの神髄であり、それは国土の大半を征する大砂漠が人の決して手なづけることの出来ぬ、人を遥かに凌駕する存在と して磁場のごとく、町をそして人々の心を畏敬の念で秘かに治めていることの証しでありました。それはまるで白昼夢を見ているかのようなマジカルな光景でし た。
そしてまたこの穢れ無き高貴な静寂こそが、広大なサハラ砂漠を王のごとく統治しているものでした。
サハラは砂の大海であり、まさに海の波がうねり押し寄せ渦巻くように、目の前に壁のように立っていた大砂丘が一夜のうちになくなります。
朝起きると、聖なるモスクのファサードを飾る永遠に繰り返される精緻なアラベスクと同じ、見事な風紋が一晩で地の果てまで描かれています。
目の前で描かれていく風紋を見ていると、何者か目に見えぬ巨大な者が宇宙から降りてくる言葉を、今まさに書きとめているかのように思えてなりませんでした。
砂漠では、ジリジリと生命を焼き尽くし、岩をも喰う灼熱に全てのものが曝され、それらのうめき声に満ち満ちているように思いましたが、驚くことにひと山を動かすほどの風の音も、またその大砂丘の崩れゆく音もなく、奇妙な沈黙の中で全てのことが為されていきます。
それは、サハラが気の遠くなるような時をかけて、岩山をき、岩を砕き、砂をついにはこれ以上は砕けないほどのなめらかなパウダーにしてしまったか らで、風の行く末を遮れるほどのものは何一つ無く、風は身をよじることも悲鳴を上げることもなく、砂共もまた、過去にもう十二分にきしり合いすぎて、もは やきしり合おうにもきしり合えるほど大きくもなく、それは遥か昔のにぎわいとなってしまったことによります。
そのせいか、1000頭をこす駱駝の大キャラバンも、まるで深い雪原を滑りゆくばかりに足音もなく、亡霊のように砂の上を歩み続けたのです。
月の世界のようなこの静寂の中に、ただ止むことなく鳴り響くのは、駱駝の鈴の音ばかりでした。
壮大な世界がその臥所から起きあがる黎明の時も、天と地ががっぷり四つの大相撲を取るように一仕事なし終えた壮麗な落日の時も、願い事の3つや4 つはかないそうな虹色の流星痕を残しながら流れていく星降る夜も、全てが秘め事のように音もなく為されて行くのは、誠に驚異でした。
私達の日常にはあまりにも音が溢れすぎ、常になにがしかの音が身にまとわりつきます。しかし時折ふっと思いもかけず深い静けさが訪れてくることが あります。しんしんと冷え込む冬の夜、最後のひとひらふたひらの雪が降り終わると、急にあたりの空間がその大気の色さえ変わるように、しーんとその深かさ をますのが感じられます。
「静かだねぇ!」と誰かが耳をかたむければ、人はその静けさの奥、遥か遠くに耳を澄ませ、かの彼岸に何かを見ることになるでしょう。
サハラの静寂は、その何かを白日の下に教えるものでした。
それは、筆が置かれる前の白紙のように、無限の可能性、永遠の自由を約束し、まだ生まれざる全てのものがその大いなる母胎の中で安らぎ育まれてでもいるかのような限りなく濃密な存在を感じさせるものでした。
そしてまた、賢治の美しい西域童話にでてくる、人の目に見えずとも大空にくまなく張られ、聞こえないが美しき響きを放ち、乳のごとく万物を育むと いう、いにしえの神話が伝える“インドラの網(あみ)”そのもののことに思われたのです。無音が奪われ去った後の空虚とすれば、静寂は荘厳なる天幕で世界 を覆い、砂粒一つにいたるまでおよそ世界に存する全てのものに聖なるしるしを刻印し、その身を空虚から救い上げるものとなるでしょう。
武蔵野の広大な栗林の花が薫る季節に、朝焼けの見事な夜明けを見とれながら、グレン・グールドの世界を驚愕させたデビュー作、ゴールドベルク変奏曲に耳を傾けていた時、このサハラの静寂に感じた同じことを体験しました。
彼の指がピアノに触れる一瞬の空白が目に焼き付き、そのただならぬ気迫に息をのみました。
この底なしの深い静寂の一点に、全ての音楽が終わった後に生まれる濃密な気が封じ込められ、今にもはち切れんばかり凝結していました。そして、時はその場に石化しその歩みを止め、音楽は永遠に歌われないかに思えました。
唖然としてその場に釘付けになっている私の頭に、その時、世界一有名な方程式、アインシュタインの宇宙定理【 E=mc2 】の5文字がシンクロナイズして、稲妻の一閃の光りに照らされたように浮かびました。そしてその眩しい光芒の中に、私は理解したのです。
【mc2】宇宙に存する万物全ての巨大なパワーが、神の御技とも思える【=】イコールの力により、エネルギーの【E】という一文字に封じ込められている、もしその【E】という一文字の封印を解けば、ビッグバーンに匹敵する大爆発が、今この場に起こるだろう。
この一瞬の【静寂】の封印も同じ、破ればこの同じ事が起こるのだ!
音楽は、爆発するであろう、決して止まない、永遠という入れ物を全て満たした後もなお鳴り続けるであろう、ついには永遠と同化してしまうほどに…。
私はその時、静寂がその玲瓏な肌の中になにを秘めているのかを悟りました。
そして静寂の実体が、その姿をかいま見せたように思われたのです。
その時、何ものかが、そう!永遠と名付けられている何ものかの顔がこちらを見つめ、あることわりを告げる気配に戦慄しました。
【時】は、この生々流転する宇宙という生き物の細胞一粒一粒を命あらしめる血液であり、この脈動する野生の穢れなき命をを入れる唯一の入れ物こそが、永遠と名付けられているものなのだ。
それは生まれもせず死にもせず、始まりもせず終わりもしない、ただ不滅なるものの別称であり、また静寂こそがまさにそのものの顔、【今】はそのものが触れる指先なのだ。
それは、目の前1m先の空中に全天一美しい、’宇宙のダイヤモンド’ベガが輝いているようなものでした。それを、理解することなどできません。
そのあまりの美しさに、呆然とその波の上を漂うことしかできないのです。
そして、私の中にも外にも分け隔てなく、静かに満ちてくるものがありました。いつしか私は、その静かに満ちてくるものの魔術にかかり、【私】という境を失い、ついには【私】そのものまでも見失しなってしまいました。
そこには、ただ一つの感覚だけが漂っていました。
それはもう、愛という名か、慈悲という名でしか表せない質感のものでした。
そして、気が付けば、いつのまにか、エーテルが流れていくかのようにゴールドベルグ変奏曲が鳴っていたのです。
生涯、私はたくさんの経験の中で、この静寂に触れることになりました。
アフリカの赤道直下の島セイシェルで、その滴る血で海を真っ赤に染めていく荘厳な落日に自らも染められながら、その日のためにウオークマンに入れ ておいたディヌ・リパッティーの「ブザンソン告別演奏会」を、33才のバースデイに聞きました。彼が最後に弾いたショパンの「ワルツNo.2」は、いつ
も同じところで止まります。そのたび毎に、私の心臓も止まる思いです。
わずか!その時の私と同じ年で白血病でなくなる彼が、世界中から駆けつけ見守る聴衆の前で、最後の力尽きてピアノの鍵盤の上に倒れてしまうからです。
残された静寂の中を、私の頭という場を借りて「ワルツNo.2」が、貴婦人の純白のレースの優美な手に引かれ、ワルツの螺旋を舞いながら天に帰っていくのを、私は見つめ続けていました。
私は時を失い、レコード盤の芯の周縁を針がむなしく回り続け、単調なリズムを永遠に刻むばかりでした。
ある秋の日“ BULA(こんにちは)、FIJI!”南太平洋のフィジーのマナ島へ、世界中のダイバーに、「鮫さえアピさんの周りではダンスを踊る!」と称えられた伝説のダイバー、アピサイ・パティさんの命日のお参りに行きました。
世界でもっとも美しい海に浮かぶ神々の集う島マナの夜、フィジアンに夕食に招かれ、村を訪れました。小さな熾火さえ共有財産のベドウィンと同じ く、フィジアンも必要最低限のもの以外あえてなにも持ちません。持つ必要がないのです。トンカチも村に一つ、回し使えばすむことで、食べ物も冷蔵庫なんて いりません。必要なとき海や畑で採れば済むのです。その夜のディナーは、生まれて初めて体験する世界中でもっとも豊かで幸せな食彩でした。
村の道には街灯などもちろんありません。手が伸びてきても分らない真っ暗な道を歩くと、家々の前のほのかな明かりの下にベンチが置かれ、人々が夕涼みがてら座るシルエットが、懐かしい影絵のように浮かびます。
夜を静かにゆったりと楽しんでいる風情です。でもなにを楽しむのか!
まだ見ぬ異国の香りさえ運んできそうな夜の涼しい貿易風を、神々の物語を読み解く星の光りを、遠く近く太古から伝わる歌を歌い継ぐ悠久の潮騒の 音、アァ!生きてるっていいなァと思わせてくれる小さな虫達の声、笑ってしまう寝ぼけ鳥のいびき、夜の花の香りや熟した果実の甘くくすぐるような匂い、
またそれらの上を漂いまどろむ幸せな夢想、そしてゆったりと安らう時の休む姿に慰められ、内にほのかに満ちてくる今ここにあることの嬉しさを!
これら日ごとに変わりゆく夜の肌触りの違いを楽しむように思えました。
とッ!黒い木の葉のシルエットの間に一つの星が見えました。
その茫洋とした淡い光りの玉こそは、世界中の星好きな人たち誰もが一生に一度はこの目で見てみたいと恋いこがれるケンタウルスの心臓に輝くω(オメガ)星団!、数百万個の太陽がボール状に密集し輝く星、宇宙の年齢よりも古いというパラドックスを持つ大銀河の美しい瞳。
それは、夜が明けるのがくやしいと人に思わせるほど、人の目を釘付けにし魅了します。
リルケは、星のことを『 光りの道のむこうの端の白い都 』と歌いました。
星が見えるということは、あまりにもあたりまえすぎる事ですが、イザ全て無くなったとすると、私達はどれだけ大切なものを失ったか分ります。
星が見えるためには、その星から何万光年、何億光年という途方もない距離を、水道管の蛇口を閉め忘れたように、光りが絶えることなく流れ続け、人のわずか3,4㎜の瞳の中へ、注がれ続けなくてはなりません。
それは一本の細い絹糸のような光りの道で、この光りの捨身の営みにより、むこうの端の壮麗な白い都と私が今まさに結ばれた証しです。
オメガと私を結ぶ光りの道が渡る宇宙空間に薄もやがかかり、もし私達の目がもっと弱い光まで見ることができれば、私達はそこに我が目を疑う驚くべき光景を目にすることになります。
母星オメガを目指しただひたすらに伸びていく一本の白金に輝く光りの糸がまともに見えてしまうからです。更には、この私の瞳という一点からおよそ 宇宙にあまねく存する全ての星に向かい、壮麗な光りの束が四方八方のびていくのを見ることでしょう。それはもはや、宇宙的なスケールの光景で、その中心に 一点人が立つとなれば、もはや人は自らがなにものに思えるのでしょうか。
周りを見わたせば、足元の一粒の小石からも、一枚の木の葉からも、天を指す人の指先からも、およそ地に存する全てのものから光りの束が延び、もやそこは宇宙の光りの海の大波が打ち寄せる岸辺と化していることでしょう。
そしてこの出来事の一部始終を見つめるものは、永遠の沈黙の中に座す偉大な静寂のみです。
人は稀に、「私は見た!」と天に向かって証言したいような気持になる経験をするものですね。
これらグールドの音楽や、またサハラの旅の日々の中などで経験した事は、それまでの私の経験の域を遥かに深くうがつものでした。
来る日も来る日も砂と太陽のみ、世界はたった2色しかなく、延々と尽きることのない砂丘の連なりに、360度地平線まで見渡せることは返って人には、不幸でした。まるで丸盆の上を円周運動しているばかりに思え、もう自分が宇宙の中のどの星にいるかも忘れてしまいます。
人はおろか何一つ生き物に出会うこともなく、波乗りをしているようなヒトコブ駱駝の背中やヤスリに掛けられるような砂漠の砂に尻や足や全身を噛まれ、自分がなぜこんな事をしていなければならないのか、返って自分はいま悪夢の中にいると思いたいぐらいでした。
この悪夢は、あの荘厳な落日に捧げるためか、星降る夜の護符とし、曙の女神の讃歌となすためか、私の心はこの極端なサハラの裏表の貌(かお)を振り子のように行き来しました。
灼熱に焼かれるこの身は偉大なサハラへの供物!と納得せざるを得ないこのような旅の日々を経て、革袋の水も尽きかけたある日、すでにキャラバンサ ライも無く、ラクダさえおびえるアッラーの燃える寝所、サハラの心臓で、この世にたった一つだけ生き残ったような井戸に出会いました。
この井戸も、砂漠の脅威にいたぶられる艱難辛苦の放浪の果てに、今ようやく私達にばったり出会えたのだと確信するほど、その発見には震えました。
果ての知れない砂の丸盆の中を、まるで酩酊しているかのように行方も定まらずフラフラ進む2点が果たして出会うものなのか? 上から見ている神々が宝の山を懸けたいぐらい、万が一にも稀有なことで、出会えば負けた神々も褒めるぐらいの一大事です。
まさによくぞ生き残った!としか言いようもなく、互いに相手の生きていることを喜び合いました。
凶暴な砂嵐が、か弱い井戸などひと飲みにし、人を絶望のどん底にけ落とす
ことなど朝飯まえです。奇跡のようなその井戸の前にひざまずけば、この世界で砂と太陽以外の唯一のもの、まさにこれこそ地球のヘソだ!と確信しました。
しかしこの奇跡の井戸は、自然ではなく砂漠の住人ベドウィンが、何千年もの昔からアフリカ大陸からユーラシア大陸に至る広大な砂漠地帯に掘り続け てきたものです。そして、この一千世代を越える壮大な歴史の中を、自らの命をそして民族の言葉を親から子へと我が血を分けて伝えてきた、その同じ熱き思い で、連綿と守り続けてきたものです。彼等はこの水と火、人が生きるに欠かせないものを、民族の存亡を掛け歴史を越えて共有財産として守り続けてきたので す。
涸れもし砂漠に呑まれもする井戸が今ここにあるためには、掘るにも守るにもどれだけの年月と彼等の命がかけられたかを思うと、永遠に山頂から転がり落ちる大岩を、人の世界にとどまったが為に上げ続けなければならぬシジフォスの営みと同じく、英雄の神話的行為に思えました。
彼等の炉の熾火に問えば、駱駝の背に揺られながら旅をし、千年二千年と燃え生き続けてきた太古からの波瀾万丈の物語を語り始めることでしょう。その火が死ぬ時は、ベドウィン民族が絶える時です。
それにしても、井戸の前に立つキャラバンを率いる古老は、なぜこの極小の一点が分るのか!
口から飛び出しそうになるこの問いを、彼の威厳が押しとどめました。私は決してその叡智の泉の水を飲むわけにはいかない。一言さえそれ問うてはならないのです。それはたやすく触れるものではなく聖なるもので、私は畏敬の念を持って彼を眺めました。
そして、大海でたった一滴の真水を探すに等しい偉業を成し遂げる彼の勇気と叡智は、まさにサハラの偉大に匹敵し、そはサハラの化身であり、いまだ に私にとって汲み尽くしえない泉となりました。その何者にも動じない黒く澄んだ瞳に今も見つめられていることは、恩師故矢内原伊作の瞳と共に、私の大きな 幸せです。
かつて対面したエベレストの威容、サハラに生きるベドウィンの古老の黒い瞳、また私のなかに脈打つ心臓、私の中では今もこの3者の驚異は等価で同一です。
ベドウィンの若者が、井戸の水を汲み上げ飲ましてくれました。椀をさしだす手は、その井戸の歴史を写して民族の誇りに満ちていました。
思いもがけず澄んだ水で、甘く冷たく私の喉を潤し、灼熱に焼けた心身にしみ渡りました。私の細胞の一粒一粒が喜びの雄叫びを上げているさなか、彼は私に井戸を覗けと申し渡し、彼の氏族にだけ伝わる鬨の声をあげました。
ベドウィンの鬨の声は氏族ごとに違い、古代より敵味方を見分けてきました。
彼のとても人の喉から出たとは思えない、槍の切っ先が鋭く光ったような鬨の声は、闇を切り裂き飛びましたがついにそのこだまは返らず、私はその井 戸の深さのいかなるものであるかを知りました。計り知れないその深みには「われはアッラーのいいなづけなり」とでもうそぶくように、白昼のただ中、地球を 突き抜いたような漆黒の闇がその謎めいた身を潜めていたのです。
太陽が井戸の真上に来たらば、井戸底の水は神鏡となり太陽より眩しく輝くであろう。井戸は巨大な砲筒となり、放たれた光りは太陽を確実に撃つ、などと灼熱と渇きに焼かれた頭が盲動しているあいだに、私はそこに私の生涯の導き手となるであろうものを見つけました。
漆黒の闇の中には針の先で突いたような光りの粒が、海に浮かぶ夜光虫のように瞬いていました。美しい!、光りはやはり光り!、たとえそれがどんなに小さくとも私達は自ずと感動してしまいます。
しかしこれはいったいナンの光りだろう? 砂漠の強烈な太陽に目を焼かれ、急に暗闇を見たために頭が、?※!@ッと、処理できず残像がちらつくのだと目をこすりましたが、確かに光りはあるように思えるのです。
その光景は、砂漠の夜をひとところ剥ぎ取って、そこに貼り付けたようなものでした。
砂漠に鍛えられたベドウィンは、鷹の目、象の耳を持つと云われます。
実際、砂漠の中の彼等の立ち居振る舞いを見ていると、私達の何倍もの能力のセンサーを持ち、自然の成り行きを読み取るのでした。
地平線の彼方まで砂の丸盆、動くもの何一つ見えないところで、「彼等が帰ってきた」と云うと、やがて揺らめく大気のカーテンを分けて、水袋をいっ ぱい下げた駱駝と共に若者達が魔法のように現れるのです。また、ベドウィンは地平線の彼方の音を聞けるとでもいうのでしょうか、突然「砂嵐が来る」
と叫ぶのです。そして小半時遅れてそれはやはりやってきます。
その時、井戸を覗く若者は「それは星だ」と私に教えました。
「エッ!」と一言いったきり、「彼等は進化してるのか!」と、あとは絶句してしまいした。
彼が砂の上になぞった星の絵を見た途端、私のなかの忘れようのない記憶や強い憧れが、たちまちその形を読み解いたのです。
そこには、私の胸の中で灯心となり、内側からぼんぼりのように私を照らしている“慈悲のチャクラ”の写し身と云えるものがありました。
その光りの粒の並びは、疑いようもなく一つの特異な星の集まり方をしていたのです。
天球を支えるアトラスの七姉妹、さやかなサファイアの炎に包まれた光りの珠に取り巻かれ、トパーズに輝くアルシオーネから一筋の光りの糸に統べられて、見事な真珠の玉が美しい弧を描きながら、今こぼれ落ちていく…、
“ 昴 ”!、万人誰しも一度この姿を見た限り、決して忘れ去ることのできない鑑、井戸のの水底には、確かにこの天の玉印が押されていたのです。
サハラはその内懐に、シバの女王の宝冠のような最も誉れ高い夜の星を隠していました。
井戸底の地下水脈に少しの流れがあるのか、昴は脈動する生き物のように瞬いていました。この自然が自ずから然りと為す美しい行為に魅せられて見つめている時、ふと私の頭にひらめくものがありました。それがあまりにも不意であったため、一瞬なにが起こったのか分りません。
私は、地の昴と天の昴を結ぶ目に見えない一本の光りの線を凝視したのです。
井戸に昴が写るためには、昴は360度の全天のピンポイントの1点、まさにこの場の天頂にいなくてはなりません。
大地の水平面に直角に立つ垂線は今、地球の中心から発し、この井戸を貫き、天頂の昴、’向こうの端の白い都’に達していました。
地球上の一点が緯度・経度の座標を持つように、天球上の星も地球の赤道を移した「天の赤道」と、その黄道との接点である「春分点」を基点にした赤緯・赤経の座標を持ちます。
昴の座標【 赤経 03h47.1m ・赤緯 +24゜06′ 】を、日時に従って大地に移せば、ナンの目印もなく迷子のこの井戸が地球上のどこの一点なのかが分る!!
あァッ!と身震いがして、まるで絶海の孤島に一人取り残された人間が水平線彼方に初めて見えた‘海でないもの’に必死で手を振るように、煮えたぎる頭と震える手で星図を調べ、地図を調べました。そしてついに小さな狼煙を目当てに船は舳先を私に向けたのです。
天頂の昴の赤緯は、地球の緯度を指しています。
北緯24゜06′ の大地の上には、【赤緯 +24゜06’】の 座標を持つ宇宙の果てまでの美しい星々が手をつないだ壮大な光りのリングが走馬燈のように回っています。
経度は?、その年月日の春分点を基点に、昴が天頂に出現するその日の時刻から割り出せる!。つまり、今この瞬間であり、私はあわてて時計を見つめました。(それはとても美しい方程式だったのに、遠い記憶の彼方に消えてしまいました、)
その時、私は神がその杖で迷える子羊にその場所を指して教えたと思いました。この日この時刻、天頂に昴が輝やく位置は、
私達はまさに“アッ=サハラーゥ=ル=クブラー”(大砂漠)のど真ん中、アポロンの火車が真東から万物の影が無くなる天頂を駆け、真西に沈む北回 帰線上のオアシス、ブルーメットへあと一日、サハラの豊かな二つ乳房の一つ、ホガール山脈のサハラ第3の高峰“アセタレン山”(標高2918m)へあと五 日、その南麓にある古代からのサハラ交易の中心地、「金と奴隷」「白い金(塩)とタカラ貝(貨幣)」が行き来した‘砂漠の真珠’キャラバンサライ“タマン ラセット”へあと七日の旅程の地にいたのです。 私はその時、ベドウィンやトゥ アレグ族やベルベル人、これら砂漠の民がなぜ砂漠に深い井戸を掘るのか分りました。命の水を得るのはもちろんですが、更に大切な命の地図を得るためでも あったのです。
私はその時、必死で精細な地図や星図、コンパスや時計を使いました。
しかし、それらがなにもない古代から、サハラを渡るキャラバンの交易はあり、砂漠を生活の場とする民は存在したのです。
無一物の彼等はなにを頼りに、人の生存を拒否する砂漠に挑めたのか。なにが彼等を助け、井戸のありかを教えるのか。
富士の樹海で迷うとつくづく思いますが(笑)、原初の人にとって知の及ばぬ域はいくらサハラの真昼であろうが暗黒であり、と同時に得体の知れぬも のへの畏怖の念から、聖域として【tapu】(タブー・禁忌の語源、はっきり印をつけられた:ポリネシアの言葉)の域を設け、一歩たりとも歩み入ることは なかったことでしょう。
しかし、人の生がいまわの際にもその中に命の永遠性への揺るがぬ意志を内
包するように、憧れ羽ばたくことを宿命づけられた人の不羈の知が、勇者の身を駆り、闇に閉ざされた未踏の領域へ、一歩を踏み出させぬわけがない。
憧れはその力強い翼を羽ばたかせ、いまわの際にも人の手を引き、生死の峠を越えさせるほどの力を持つ。また、人はそのことを祈るのだから!
それは宇宙が、人という種に与えた特別な本性だと思うのです。
富士が生きて活動し山上の雲を真赤に染め上げていた時でさえ、身の危険を顧みず、やむにやまれぬ内なる憧れに駆られ登る人がいました。
砂漠の民もその嚆矢において、ウイキョウの茎の中に神の火と知を隠し持ち人に与えた、かのプロメテウスのような人がきっといたことでしょう!
彼等ベドウィンの’ハーマーサ'(剛勇と熱情)と呼ばれる誇りの由来となる
勇気ある人々の列が、川の流れのように今に続いています。
膨大な年月と命を掛けて営まれた人々の体験の集積と、そこから人間の叡智が汲み上げた知の堆積!、彼等の命は民族のこのような【知】の地層が厚く積み重ねられた揺るがぬ大地の上に立っているのだと思いました。
その大地の上に立つ限り彼等は、不毛のサハラを神の贈り物といえるのです。
キャラバンの古老の瞳の中の明るさは、まさにこの成熟した時の現れでした。
私は人間の知とはいかなるものであるか、いかなるものであらねばならないかを切実にそのとき思い知らされたのです。
アメリカ大陸・五大湖周辺に生息する蝶、‘オオキマダラ’は生殖時期に、壮大な渡りをする蝶として知られています。五大湖から大陸を縦断し、遥かメキシコのなぜかある山の一つの斜面にだけ何十億羽と飛来します。
紅葉など無い亜熱帯林の緑の山が、鮮やかなイエロー一色に染め上げられる
そうです。そして産卵し、親は死にます。ところが、その子は羽化すると飛来した親はいないにかかわらず、ルートを逆に正確に五大湖まで帰るのです。
人でさえ道に迷うのに、1㎜もない蝶の頭のどこに、渡りの習性が伝えられ、自らは未知の飛来のルートを4000㎞彼方まで、迷いもせず帰るのか、また帰らねばならないのか。これは形質的な遺伝を越えた蝶の文化の遺伝!、生命の神秘に目を見張ります。
この地球上に人類が種として成立して、およそ100万年といわれています。
今ここに私が在るためには、約5万人ぐらいの母が命を手渡しで繋がなければ、私はいません。人類の平均寿命が二十歳の壁を越えることができるのに、ほとんど100万年の時を費やしたのでしょう。
私の【太古の母達】は、不毛のサハラと同じ逆境の中を逃げまどい、産み落とし、命をそれこそ命がけで守り続けてきたことでしょう。
ナチの将校の銃口の前に立ち、我が背を向けて胸に抱く幼子を守るアウシュビッツの母の姿を忘れられません。
蝶でさえとてつもないものを伝えるのに、人のこれほどの思いが、時を貫き人の魂の流れの中を伝わらぬわけがないと思うのです。
生命の大河の中を伝わるものは、ただ命の綱である大切な遺伝的な形質のみならず、そのみなも(水面)の上を川霧の流れるように、目に見えぬ、言葉 や文化、さらには切なる思いを託した生きた証しや、久遠の中に瞬間スパークしたパッション、人々の喜びや悲しみ、憂愁や苦悩、祈りや歌声、酒や香水や薔薇 の香り……、それらの総体が人の【知】であり、共に流れ伝えられ、立つ人を支える豊かな大地になっていくのだと思いました。
そして、いつも思います、膨大な波打つ水の堆積を前に、初めて“ ウ ミ ”と口にした人のことを!
朱や金や韓紅(からくれない)や茜色の空が、やがて暮色蒼然として、人家に一つ二つと懐かしい明りが灯っていくように、もの達一つ一つに言葉の明りが灯っていく様は、どれだけ私の心を励ましたでしょう。
人の知の黎明期、人はどのようにして【知】を獲得していったのでしょう。
幼い頃は、全てのことが何故?で始まりました。いつも夜、暖かいお布団に入って夢路に落ちる前、そんなことに想像をふくらませていました。
遥か遠い時を隔てたその人の中に起こった、宇宙の中にも類い稀な美しい出来事、闇の中から生まれた星が初めての光りを放つような知の誕生の瞬間を体験したいと恋いこがれました。
ある時には、天空の‘ソフィア’(知の女神)の美しい胸元を飾る‘明けの明星’、‘イデア’(存在の根拠)の白銀の光りのようなその人が、そばに立つ気配を感じるほどに!
そして後日、私はその光りを教える人に出合うことになりました。
『人を取除けてなおあとに価値あるものは、作品を取除けてなおあとに価値ある人間によって作られるような気がする』
このとおり辻まことは、「作品を取除けてなおあとに価値ある」人でした。
恩師についてゆかりの場に度々訪れました。そこが都会のバーであれ、ビストロであれ、山小屋であり、またゆかりの山河そのものであっても、かの人の残り香が色濃くその場を染めていました。場はそのえにしを失えば、その存在の意味さえ失ってしまうと思えるほどに。
人が生きる、時空の軸が十字架に交わるところ【 Here Now 】!
この【今】という一点の深さは、その座標軸に添って視野を広げていけば、被造物の思いを遥かに超えて、ついに宇宙の全ての命運を司る神秘の場と化してしまいます。辻まことの視野は常にそのような遥かな深みから、今の中に落ちてくるように思いました。